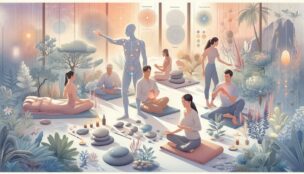冷え ツボ 刺激で体が温まる セルフケアの決定版です。
冷え性で手足が冷たい、夜なかなか寝付けない、体のだるさが続く…そんな悩みを抱える人は少なくありません。冷えの原因の多くは血行不良によるもので、体の熱を効率よく作り、運ぶ力が低下していることにあります。
体を温める食事や適度な運動も大切ですが、東洋医学で古くから伝わる「ツボ(経穴)」の刺激は、自宅で手軽にできるセルフケアとして即効性が期待できる方法です。
冷え ツボ 刺激で体が温まる
本記事では、特に血流を促し、全身を内側から温める効果がある代表的なツボを厳選。ツボを「痛気持ちいい」強さで刺激することで、冷えやだるさの改善につなげ、体のポカポカ感を実感できる方法をご紹介します。
冷えの解消に効果的なツボ刺激は、体を温めるセルフケアの定番です。手軽にできて、全身の血行を促進し、冷えの改善が期待できる代表的なツボをご紹介します。
冷えに効く体のツボ(セルフケアの決定版)
1. 合谷(ごうこく)
- 場所: 手の甲側で、親指と人差し指の骨が合流する手前のくぼみ。
- 効果: 全身の血行促進、特に手先の冷えや肩こり、頭痛、ストレスの緩和に役立ちます。
- 刺激方法: 反対側の手の親指で、骨に向かってゆっくりと「痛気持ちいい」程度の強さで5秒ほど押してから、ゆっくり離します。
2. 三陰交(さんいんこう)
- 場所: 内くるぶしの一番高いところから指幅4本分上、すねの骨(脛骨)の後ろ側のきわ。
- 効果: 下半身の冷えやむくみ、生理痛など女性特有の不調の改善に効果的で、体の内側から温めます。
- 刺激方法: 指の腹で優しくじんわりと押したり、お灸で温めるのもおすすめです。
3. 湧泉(ゆうせん)
- 場所: 足の裏。足の指を曲げたときにできる、つま先からかかとまでの約1/3の土踏まずのくぼみ。
- 効果: 新陳代謝を高め、足元の冷えやむくみ、疲労回復に効果があります。下半身の血流を促し、体がポカポカしやすくなります。
- 刺激方法: 手の親指で5秒ほどゆっくり押します。朝起きた時や寝る前に行うのがおすすめです。
4. 関元(かんげん)
- 場所: おへそから指幅4本分下、体の中央線上。
- 効果: お腹の冷えや下痢、足腰のだるさに効果的です。血行促進や利尿作用もあり、体が冷えて眠れないときにもおすすめです。
- 刺激方法: 手のひら全体でゆっくり5秒ほど押します。カイロなどで温めるのも効果的です。
ツボ刺激のポイント
- 強さ: 「痛いけれど気持ちいい」と感じる程度の強さが目安です。
- 押し方: ゆっくり息を吐きながら5秒ほど押し、息を吸いながら力を緩めます。これを数回繰り返します。
- タイミング: 冷えが気になるときや入浴後など、体が温まっているときに行うと効果的です。
これらのツボを日々のセルフケアに取り入れ、冷え知らずの温かい体を目指しましょう。